全域踏破はあきらめたのですが、今回はミーハーらしく北側の山腹にある笠松公園からの『股のぞき』にと挑戦しました。「天と地が逆に見え、その間に橋が・・・」という股のぞき。時の為政者の圧制に苦しむ庶民が、そこに世直しを感じた歴史と重なり、感慨深いものがありました。ついついお隣でのぞいていた方の足を拝借してパチリ!
右の写真は、アメリカや大企業にばかり目を向けていた政治が、今や変わろうとしている現在を切り取った「つもり」の一枚になったのでしょうか??


少し足を伸ばして、伊根の道の駅から「釣り馬鹿日誌」でおなじみの「舟屋」を見学しました。「現場に行ってみたい」と思ったのですが、「あそこへ行っても、家々はみな民家で、しかもここから見える景色とは違い、玄関側が見えるだけですよ。」の説明に、納得のあきらめでした。お金を出せば遊覧船もあるようでしたが・・・。


 次はお隣の舞鶴市です。宮津市からの道々、海岸の美しい景色を眺めながらのドライブでした。途中で美味しい海鮮丼を堪能、最後に峠を越えたところに舞鶴市はありました。どうやら西舞鶴と東舞鶴に、ここも間に峠を挟んで分かれているようです。西舞鶴はかって細川藤孝(幽斎)が活躍し、江戸期には京極家、牧野家が城(田辺城=舞鶴城)を置いて、城下町として栄えたところのようです。
次はお隣の舞鶴市です。宮津市からの道々、海岸の美しい景色を眺めながらのドライブでした。途中で美味しい海鮮丼を堪能、最後に峠を越えたところに舞鶴市はありました。どうやら西舞鶴と東舞鶴に、ここも間に峠を挟んで分かれているようです。西舞鶴はかって細川藤孝(幽斎)が活躍し、江戸期には京極家、牧野家が城(田辺城=舞鶴城)を置いて、城下町として栄えたところのようです。
東舞鶴にさしかかってしばらく、左側に見慣れない景色が広がります。灰色の巨大な船がずらずらと続くのです。自衛艦の群れです。「どうして??」という疑問は少しの間でした。「そうか。ここは呉(広島県)などと同じく、戦前は巨大な軍港だったんだ。」と思い至ったのです。
それが戦後60有余年しても、自衛隊と言う軍隊が占拠している実態があるもののようでした。う~ん、恐い景色です。
まず寄ったのは「赤レンガ博物館」です。「おや、あの門のアーチなど、アイビースクエア(倉敷市)と似た雰囲気だなー。もしかしたら同じ設計者か?」などと考えながら中へ。
そこは世界中で家の建築材料として広く使われているレンガの歴史をまとめて展示してある博物館でした。人類最古の文明であるシュメール(メソポタミア)のジグラット(聖塔)から始まり、現代の西洋文明の建物の多くを形作っている「レンガ」。日本へは仏教伝来とともに伝わり、明治以来の近代建築物に多く使われてきたそうです。それぞれの建物が写真と解説つきで1階、2階を埋めていました。
これまでレンガについてまとめて考えたことの無かった私にとって大変参考になりました。
ただ、この博物館をはじめ、東舞鶴に集中的に残る赤レンガの倉庫群は、明治以来の日本海軍の軍用倉庫で、兵器などが収められていたと聞き、いっぺんに興味を失った私ではありました。


舞鶴でもう一箇所訪ねたのがここでした。太平洋戦争終了時、アジア、太平洋全域に取り残された日本人は、一般人、軍人を含めて、約250万人を越えていたそうです。その人たちの引揚はそれは悲惨なものでした。
そしてその中でも中国東北部(旧満州)に取り残された旧軍人たち(その多くは現地召集の補充兵で、軍隊とは名ばかりの人々だったそうです)のうち、約55万人が旧ソ連の各地に抑留され、強制労働に従事させられました。極寒の地、それはそれは厳しい生活を余儀なくされ、多くの人々が亡くなりました。
 その歴史と、それから10年かけてここ舞鶴へと帰還してきた約50万人の歴史を残そうと、この記念館が建てられたそうです。
その歴史と、それから10年かけてここ舞鶴へと帰還してきた約50万人の歴史を残そうと、この記念館が建てられたそうです。
まずは、私もカラオケで時々歌うあの「岸壁の母」のメロディーが出迎えてくれたのには、ちょっと複雑な気持ちにさせられました。個人的には私の父は関東軍(当時満州に駐屯していた日本軍)にいたのですが、少し前に演習で負傷して、内地の陸軍病院に入院、除隊したため、抑留からはまぬがれたのですが、それでもシベリア抑留は、知りたいけれども触れたくない・・・テーマではあります。
その悲惨さは折に触れて聞かされてきたのですが、詳しくはほとんど知りませんでした。何と、シベリア全域、サハリン(樺太)は勿論、遠くモスクワ近郊、コーカサス地方、そして原爆実験上のあったセミパラチンスク近郊にまで、元日本兵たちが分散抑留されたいたのです。
そして、その人たちがこの舞鶴港へ帰った来た帰還船。当時多くの肉親たち、母や妻たち、子達がこの丘の上から、夫や子達の帰りを待ち続けたそうです。岸壁の母、岸壁の妻たちは、多数に上ったそうなのです。歌のモデルになったのは、端野いせさんという女性でした。
「もう2度と戦争などをおこしてはならないという気持ちを後世に伝える為に」設置されたこの記念館です。 旧巨大軍港の地で、良い経験をさせていただきました。(2009,9)



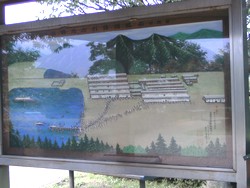


 まずは天橋立。平安時代から歌にも読まれ、日本を代表する名所の1つです。
まずは天橋立。平安時代から歌にも読まれ、日本を代表する名所の1つです。



 次はお隣の舞鶴市です。宮津市からの道々、海岸の美しい景色を眺めながらのドライブでした。途中で美味しい海鮮丼を堪能、最後に峠を越えたところに舞鶴市はありました。どうやら西舞鶴と東舞鶴に、ここも間に峠を挟んで分かれているようです。西舞鶴はかって細川藤孝(幽斎)が活躍し、江戸期には京極家、牧野家が城(田辺城=舞鶴城)を置いて、城下町として栄えたところのようです。
次はお隣の舞鶴市です。宮津市からの道々、海岸の美しい景色を眺めながらのドライブでした。途中で美味しい海鮮丼を堪能、最後に峠を越えたところに舞鶴市はありました。どうやら西舞鶴と東舞鶴に、ここも間に峠を挟んで分かれているようです。西舞鶴はかって細川藤孝(幽斎)が活躍し、江戸期には京極家、牧野家が城(田辺城=舞鶴城)を置いて、城下町として栄えたところのようです。

 その歴史と、それから10年かけてここ舞鶴へと帰還してきた約50万人の歴史を残そうと、この記念館が建てられたそうです。
その歴史と、それから10年かけてここ舞鶴へと帰還してきた約50万人の歴史を残そうと、この記念館が建てられたそうです。